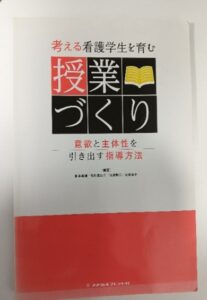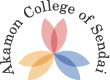第148回初心に返る ~「授業づくり」を再読して~
看護基礎教育において授業とは、講義、演習、実習をさします。
授業は看護過程と同様に、達成すべき目標を設定し、さまざまな方法を用いて、学生の看護師としての人間的な成長発達を促すために展開します。
看護教員は看護実践能力と教育実践能力が必要であると言われています。看護教員になってから、それらを身に付けるのではなく、それまでの看護師としての臨床経験や、“専任教員養成講習会”で(看護専門学校の専任教員は受講必須です)、授業の組み立て方などを学びます。
学生は看護学校に入学し、様々な体験を通して看護という新しい認識世界を形成し、技術を習得しますが、それらを支援するのが教員の仕事です。あくまでも学びの主体は学生であり、学生が学ぶことに困難が生じているならば助けるのが教員の仕事と考えます。学生が「ああ、そういうことだったのか」とわかることを繰り返し体験できるよう支援することで、学生はわかることの経験を蓄積していきます。ひとたび、わかることがわかると、それは楽しい経験となり能動的に学習していくとされていますが、実際は難しいようです。日々の学校生活のなかで状況判断や文脈(ストーリー)の中で考え、自分が看護師だったらどのように看護するだろうか、などと考えることを習慣づけることは、将来看護師になる学生には大事な思考の訓練となると言われています。そのような授業を展開したいものですが、私には容易なことではありません。私は現在、実習で学生を指導することが主な仕事ですが、沢山の影響因子が複雑に絡み合い、思い通りに授業展開できないことのほうが多いです。今回、参考にした本を読み返し、初心に返り学生にとってより良い指導を行えるよう今後も研鑽したいと思いました。
キーワード:学習支援、能動的学習
参考図書 「考える看護学生を育む授業づくり 意欲と主体性を引き出す指導方法」
[編著] 新井英靖/荒川眞知子/池西靜江/石束桂子
2013年7月22日 第1版第1刷 メジカルフレンド社