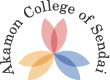第144回こころのめ
今回は教育への想いというテーマをいただきましたので、自身の実習エピソードをふまえつつ、教育で大切にしている想いを共有したいと思います。
私にとって実習での出会いはどれもが思い出深いものなのですが、全盲の患者さんを受け持たせていただいた時のことを書いてみます。
ある時、患者さんとの会話で自分だけ見える状況がもどかしく感じられ、目を閉じて会話をしてみたのです。
そして目の前にあるものをイメージしてみました。
すると、さっきまで見ていたはずの病室の壁やドアとの距離感、床頭台のレイアウトすら曖昧で、何より患者さんがどんな表情で会話をしているのか分からず、なんとも心許ない気持ちになりました。
同時に、患者さんは日時をどうやって確認しているのか、普段は着たい服を選べているのだろうか、間違った薬を飲むことはないのだろうか、昼夜問わず真っ暗な視界のなかで夜になったら眠くなるのだろうか、そもそも私の姿形を知りようがないではないか…!という具合に、疑問と反省とが次々と浮かんできました。
そうこうしているうちに、患者さんがぽつりとこぼした言葉に衝撃を受けました。この方はテレビの音声が流れるラジオをいつも側に置いているのですが、「最近はテレビがつまらなくなった」と言うのです。
私はこの言葉の意味することがよく分かりませんでした。
理由を尋ねると、近頃のテレビ番組は暴力シーンが多く、そのような音を聞くのは決して良い気分にはならないのだと教えてくれました。
この時に感じた私の気持ちが伝わるでしょうか。
感覚に不自由なく生きているからこその盲点、つまり、気づかないだけで私にも見えていないものがあると自覚した瞬間だったのです。前述したように、私は目が見えていても見えていない、もしくは見過ごしてきたものが沢山ありました。障害のあるなしに関わらず、不自由さは自分自身のありようなのだと気付かされた出来事でした。
さて、人の生死が交差する場は綺麗事ばかりではなく、普通に暮らしていれば目にすることのない患者さんの苦悩を垣間見ることがあります。この時に自分が患者さんに対してどうあるか、これこそが看護の本質だと思っています。正解のない問いに向き合うのはエネルギーを要しますが、学生のみなさんには立ち止まって考え、気づき、真摯に向き合う強さを培ってほしいと思っています。考えた先に何かを見つけた時には、きっと人生を豊かに力強く歩んでいけるような手がかりが得られるはずです。
そして、たとえ目に見えないものだったとしても、気づける感受性と洞察力を磨いていってほしいと思っています。
どうぞ、みなさんそれぞれの「心の芽」を育んでいってください。
私自身は、学生と共に考えていける存在でありたいといつも思っています。
最後に、私が大事にしている恩師の言葉を紹介します。
「患者さんの前にはフラットな気持ちで立ち、発せされたサインを見逃さないこと。
見たいものだけ見ずに、自分の物差しを伸ばしていきなさい。
そして何かをする時は失敗を恐れたり、自分の評価を入れたりして行動を制限することのないようにしなさい。
考える人になれ。ただの作業者になるな。 」

写真は他大学で初めて実習指導を担当した学生たちからいただいた折り鶴とメッセージです。実習ではどんなにか大変だったことでしょうに、忙しい合間を縫って気持ちをしたためてくれた学生たちの心遣いは何ものにも代え難い宝物です。今春、卒業を迎える当時の学生たちに思いを馳せつつ、またどこかで会えた時には成長した自分でいたいと、毎日を大切に過ごしています。